「フィジタル・リテール(Phygital Retail)」は、デジタル(オンライン)と実店舗(オフライン)を組み合わせたアプローチを指す用語です。本記事では、デジタルテクノロジーと実店舗それぞれの利点に触れながら、よりよい顧客体験を提供するためのフィジタル・リテールに関する情報をお届けします。
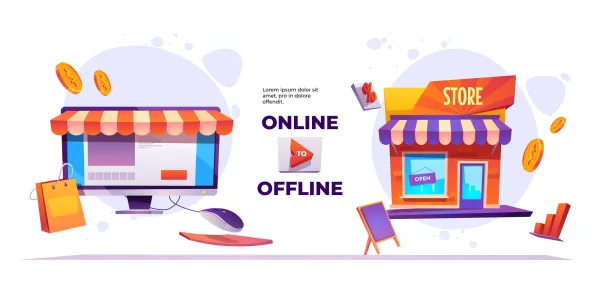
目次
「フィジタル・リテール」(Phygital Retail)は、「フィジカル」と「デジタル」を組み合わせた用語で、2010年代後半から注目され始めました。リアル店舗とデジタルの統合が進み、顧客により豊かな購買体験を提供する概念が浸透する中で、この用語が使われるようになりました。
また、過去には類似のアプローチを示す用語として「オムニチャネル」、「マルチチャネル」などがありましたが、「フィジタル・リテール」とは、小売業者が消費者と効率的に関わり方を検討する際の新たな考え方です。
生活者のほとんどは、実店舗だけでなく、ECを利用して日々生活しています。
今日使いたい食材や明日着ていきたい洋服などは実際の店舗で購入し、冷凍食品や予備の生活用品など今すぐなくても困らないが購入しておきたいアイテムは、ECで家に届くようにして購入することでしょう。
スマートフォンが普及した現在の日常生活のほとんどは、デジタルで解決できることでしょう。しかし、実際の商品を確認したかったり、使いたいタイミングなどではオンラインで解決できるがオフラインで解決した方が都合の良いものもあり、生活の中でオンラインとオフラインが混在しています。この2つは非常に密接に絡み合っており、その境目や違いがはっきりしないことが多く見受けられます。
フィジタル・リテールとは、よりより顧客体験の提供を目的にして、オフラインとオンラインを融合させるアプローチです。これはそれぞれのメリットを取り入れ、より良い体験を提供して商品へ満足してもらうことやファンを増やすことを目的とした際の戦略として使用されることが多いです。
ここ数年、「ECが従来の店頭型の小売よりも便利でテクノロジーを活用することが、利用者に取ってメリットになり、その可能性は今後も広がり続ける。」といった情報を目にする機会も増えています。
ECは一度に検索と商品・サービス比較を同時に実施できる利点があります。
また、オンラインであれば日本未入荷の海外製品でも手に入れることが可能になります。従来の店舗での販売方法で同じように商品を提供するには、参入したことのない海外へ店舗を構える必要があり、金銭的にも時間的にもコストの高い動きになってしまいます。
ECの利点は距離や時間にとらわれることなく販売が出来ることに対して、従来の店頭での販売方法が得意とするのは購買に必要な体験(試着・販売員の説明)、ブランド・ロイヤルティの向上、ブランドの認知度向上が挙げられます。
例えば、ある化粧品メーカーが短期出店として、路面に1ヶ月間、店舗をオープンしたが店舗では当初の売り上げ目標には到達していませんでした。しかし、同じ期間にその会社のウェブサイトでは新規顧客からの売上が実店舗よりも多く出たとします。この場合、売上を見る限りでは、その実店舗の展開は失敗と判断されることでしょう。しかし、実店舗が売上は出していないが、数千人の新規顧客にブランドを知ってもらえるきっかけを作っていて、それをきっかけにオンラインショップで購入した方がいたとしたら実店舗の展開の評価はまた変わってくることでしょう。
さらに、店舗訪問後、当日の夜にECを訪れて購入、その後も数ヶ月に1度オンラインショップで購入し、実店舗に来たことがある方がWeb広告経由の顧客よりも多くの購買をしてくれているとしたら、どのような評価になるでしょうか。最初に店頭でブランドの世界観や使用している素材の良さ、自分好みの発色や使用感であることを理解出来たからだとしたらどうでしょう。
このように店舗での体験をしてもらうことで、セールや期間限定クーポンなどのウェブ広告経由による1回限りの購入ではなく、ロイヤルカスタマーとして長期間におよび購入し続けてもらえるケースも発生しています。
オフラインとオンラインを隔てず、共通の顧客体験を考え、戦略を策定し、実行・判断していくことがフィジタル・リテールの目指す世界観です。
フィジタル・リテールの事例
「Instagram×ポップアップストアのシナジーで最高売上に!「神戸洋靴店」の販売戦略とは」
実店舗は、ECでは再現できない体験を提供する機会をブランドにもたらしてくれます。
実店舗の展開とは、商品を購入するだけであれば、オンラインで出来るため、より記憶に残りやすいような体験を提供することが重要になってきています。
体験によって、顧客のブランド・ロイヤルティを向上させ、継続的に商品を購入してもらうことは、どの企業にとっても優先して達成したいことでしょう。ブランド・ロイヤルティを高める上で1番重要なことは、ブランドが提供できる体験にあるのは間違いありません。
ECには多くのメリットがありますが、実際に街や商業施設などで、実物を確認し、ブランドスタッフから商品の説明を聞いたり、直接ブランドの方からブランドの商品に込めているメッセージに触れるといった、対面や実際に商品に触れられる場所でしか体験できないことを再現するのは難しいことでしょう。
オフラインとオンラインでの小売戦略を統合的に実施することで、それぞれの強みを活かして、両方の可能性を最大化することができます。
オフラインとオンラインの融合に関して、戦略のアプローチをいくつかご紹介します。
靴や服のサイズは均一的な表記に見えて、ブランドごとに微妙にサイズ感が違っていたり、肩幅や腕の長さなど個人差が生じますが、店頭や自宅で専用の機械やアプリを用いて個人の身体情報を計測、データとして保存することでそれ以降の購入の際にオンラインショップで見ている商品が自分にとってちょうど良いのか大きいのか、小さいのかを判断できるようになります。
今までサイズを確認するために店頭に足を運んでいたことがなくすことができ、利便性の高さを顧客に提供することができます。
クリックアンドコレクトとは、オンラインで購入し、店舗や宅配ボックス、ドライブスルーなどの自宅以外の場所で商品を受け取るようにするショッピングスタイルおよびその仕組みのことをいいます。
受取体験の向上、店舗での購入の即時の満足感とオンラインショッピングの利便性を提供しています。
実店舗内でも製品に関するオンラインユーザーのレビューを見せることで、ブランドは価値を提供し、顧客の意思決定にアプローチできます。
仮にその仕組みが実店舗になかったとしても顧客はスマホを使ってアプリやWEBサイトでオンラインのレビューを見るでしょう。その際に実店舗に置いていない他の製品に気をとられるかもしれません。
その場で製品のオンラインのレビューを見せてあげるのはとても重要な要素となります。
バーチャルリアリティと拡張現実技術は、デジタルとフィジカルの間に位置しています。
店頭で服を「試着」するためや部屋に置く家具のサイズや配置、色味などを「確認」するために拡張現実を使用したり、顧客をブランドのストーリーにさらに深く没入させるためにバーチャル・リアリティを使用したりと、その可能性は多岐にわたります。
ブランドは短期出店(ポップアップストア)を利用して新規顧客の獲得やブランドロイヤルティの向上などをしてきました。
D2Cと呼ばれるビジネスモデルの台頭、コロナ禍におけるネットショップ開設数の増加もあり、店頭販売の在り方も販売チャネルとしての手段だけでなく、購入者に対するアンケートの実施と紐付けたり、オンラインショップでの再購入を目的とした、EC限定のクーポンを配布するイベント実施など、オフラインとオンラインを行き来した取り組みをしやすくするためのチャネルとして、見直されつつあります。
ポップアップストア出店を利用することで、季節需要に連動したキャンペーン、出店に向けた商圏のテストマーケティング、新商品・新サービスのドッグフーディング等、顧客により優れた体験を提供するための実験が可能となります。
フィジタル・リテールが指す世界観に対するアプローチは、今後も様々な可能性がうまれてくることでしょう。共通しているのは、よりよい顧客体験の提供を目指すという目的です。ECと実店舗、どちらでも生活シーンに応じて、相談・購入できる顧客体験設計はどのようなブランド・サービスであっても不可欠な考え方です。
SHOPCOUNTER MAGAZINEでお届けしている情報も参考にしながら自社ブランド・サービスにおける最高の顧客体験設計を定期的に考えてみてはいかがでしょうか。
出店戦略・物流・CRMの観点から、年商フェーズに合わせ、取るべき成長戦略について、各領域に精通した事業担当者3名が「自分だったらどういう話をするか?」というテーマで議論しました。
詳細はこちら
「SHOPCOUNTER」は、ポップアップストア・催事・展示会などの出店/出展場所の予約がオンライン上でできるプラットフォームです。ショッピングモール、スーパーマーケットなど様々な商業スペースの検索・予約が可能です。

ポップアップストア・催事イベントにおすすめなスペースや、ノウハウ・事例を紹介いたします。

2020年10月28日

2020年5月13日

2021年5月18日

2025年1月24日

2020年9月17日

2023年12月11日

2025年1月31日

2017年2月28日
2016年5月12日
2025年5月30日
2020年2月14日
2025年6月2日
2025年1月27日
2025年10月20日
2024年4月28日
2025年6月3日

2025年12月8日

2025年12月4日

2025年11月4日

2025年10月20日

2025年10月20日

2025年10月7日

2025年9月26日

2025年8月27日