ショッピングモールとショッピングセンターは耳馴染みがある言葉ではあっても、それぞれの意味や特徴などをきちんと把握している方は少ないかもしれません。本記事では現代の消費において中心ともいえるショッピングモールとショッピングセンターについて、基本的な定義や歴史、違いと特徴、今後の展望と活用法をご紹介します。

ショッピングモールとは、さまざまな店舗が一つの建物に集結した複合的商業施設です。飲食店や小売店に加えて、映画館をはじめとした大型のエンターテイメント施設なども併設されているのが主な特徴です。
日本のショッピングモールは、ショッピングセンターの一形態であり、「モール型ショッピングセンター」と呼ばれることもあります。「モール」は英語で遊歩道や通りを意味しており、ショッピングモールの構造として長い通路を備えているのが特徴的です。
昨今では、ショッピングモールはショッピングセンターと比べて規模が大きい商業施設を指すようにもなりました。なお、ショッピングモールが誕生したことで、通路のないコンパクトな商業施設をショッピングセンターと呼ぶようになった説もあります。
ショッピングセンターは、地域密着型の商業施設。主に日常使いが可能なテナントで構成されています。
ショッピングセンターはショッピングモールと異なり、定義が日本ショッピングセンター協会によって決められているのが特徴。
その定義は、次の通りです。
・小売業の店舗面積について1,500平方メートル以上
・キーテナントを覗いて10店舗以上ある
・キーテナントの面積はショッピングセンター全体の面積の8割ほどを超えていない
ショッピングモールとショッピングセンターの違いを下記にまとめました。
| ショッピングモール | ショッピングセンター | |
| 施設の規模 | 通路があり横に長い構造 | 通路を持たず縦長にコンパクト |
| 構造 | 複層階構造 | ところによっては平屋構造 |
| 立地 | 都市型もあるが郊外型が多い | 郊外型もあるが都市型もある 住宅地に立地した施設もある |
| 顧客層 | 若年層からファミリー層、高齢者まで幅広い年代 | 30~50代 |
ショッピングモールの歴史は、1920年代のアメリカにて不動産業者が初めて開業したショッピングモールから始まったとされています。当時、アメリカでは車が生活に浸透していき、都市部から郊外へ生活の拠点が移動していったのです。
これに伴い、一度に必要な買い物ができるように小売店を集結させた大規模な店舗・ショッピングモールが、広々としたアメリカの郊外の土地に誕生しました。ショッピングモールはアメリカにおいて、特に1950年代後半から60年代にかけて、郊外で急速に発展していったのです。
日本においては、1980年代以降に車を利用する人々が増加したことで、大規模な駐車場を併設したショッピングモールが郊外に数多く建設されました。日本における代表的なショッピングモールは、1981年4月にオープンした「ららぽーと」(当時はららぽーと船橋ショッピングセンター、現在はららぽーとTOKYO-BAY)や、1992年11月に1号店(イオンモールつがる柏)がオープンした「イオンモール」が挙げられます。ららぽーととイオンモールは、日本全国に広がりを見せているショッピングモールです。
ショッピングセンターの発祥は、1922年のアメリカ・カンザスシティから。不動産業者のJ.C.ニコルスが手掛けたカントリー・クラブ・プラザが、世界で初めてのショッピングセンターといわれています。
日本においては1954年(昭和24年)に、当時アメリカが統治していた沖縄に誕生したプラザハウスショッピングセンターが初となります。日本企業が最初にオープンさせたショッピングセンターは、大阪府に誕生したダイエー庄内店です。以降は農村部における幹線道路沿いや、工場の跡地に大型のショッピングセンターが続々とオープンしました。
日本のショッピングセンターは、駅ビルや交通渋滞の緩和のために作られた地下街との融合、ところによっては地元商店街と連携し、今日まで発展してきました。
ショッピングモールは、1980年以降に自動車の利用者が増加したことで、車社会に対応するため、広い駐車場を備えたショッピングモールが郊外に次々と建設されるようになったのです。
現代においては、ショッピングモールはコト消費といったニーズや、テクノロジーを活用してより便利に使いたいといった顧客のニーズに対応し、進化している施設もあります。
ショッピングセンターに関しては、高度成長期には郊外においてワンストップで買い物やサービスを受けられるショッピングセンターが増えてきました。
バブル期に入ると都市部をメインに、ファッションビルや駅ビルといったショッピングセンターが誕生。バブル崩壊後には大型化と多様化により、エンターテイメント施設などを併設したショッピングセンターや、非日常的な空間を演出したショッピングセンターなどが増加していったのです。
最近ではショッピングセンターのニーズが変わり、郊外に出なくても駅で買い物が済む・モノ消費からコト消費にシフトしていきました。特にショッピングセンターはただ買い物ができる場所から、映画館やアミューズメント、エステや医療の施設などを有し、生活の一部として利用できる場所も求められています。
ショッピングモールは多くの場合、郊外に立地しています。なぜなら、郊外にあるショッピングモールは車社会に対応するべく、広大な敷地に広い駐車場を構える必要があるからです。広々とした駐車場により車で訪れやすくなり、周辺地域から多くの人々が集まっています。
また、ショッピングモールはさまざまな地域からアクセスしやすい場所や、高速道路のインターチェンジ付近に位置することも多いです。
ショッピングセンターには「郊外型」と「都市型」が存在します。郊外型ショッピングセンターは、主に車で訪れる人々が対象です。一方、都市型ショッピングセンターは都市部や住宅街に密着しており、電車やバスでの来訪者をメインターゲットにしています。
都市型ショッピングセンターは土地の制約があるため、小規模から中規模の施設が一般的ですが、中には再開発や工場などの跡地を利用して大規模な店舗が建設されるケースもあります。
ショッピングモールとショッピングセンターは、施設の規模や構造に違いがあります。
ショッピングモールはショッピングセンターと比較して、店舗の規模が大きな施設が多く、広大な面積に複数階構造です。日本におけるショッピングモールは、商店街のように横の長い構造で通路がある構造となっています。
ショッピングセンターはショッピングモールが誕生したことで、通路を持たずコンパクトで縦長な施設を指すようになりました。ショッピングセンターの中には、平屋構造の施設もあります。
ショッピングモールは商業ビルのように飲食店やファッション・コスメなどの小売店だけでなく、映画館やゲームセンターなどのエンターテイメント施設やアパレル、有名ブランドの店舗、家電量販店など店舗の種類が非常に豊富です。
ショッピングセンターは規模によって店舗の数が異なりますが、スーパーマーケットや日用品が中心。その他にも、ドラッグストアに100円均一ストア、クリニック、美容室をはじめとしたサービスの店舗が入っているショッピングセンターもあります。
ショッピングモールは買い物ができるだけでなく、飲食店や遊べる施設が充実。そのため、顧客はレジャー感覚を求めたり、家族で一日中楽しんだりするために訪れています。また、ショッピングモールは、雨の日でも気にせず過ごせる屋内施設として高い需要があります。
一方、ショッピングセンターは食料品や生活必需品など、日常に必要なアイテムを取り扱う店舗が中心。ショッピングモールとは異なり、実用性と利便性が重視されており、日常使いとして利用されています。
ショッピングモールの進化には、以下の2つのポイントが重要です。
1つ目は、エンターテイメント性とテクノロジーの活用。現代の商業施設では、単なる商品販売を超えて、消費者にとって独自の体験を提供することが求められています。
具体的には、エンターテイメントとショッピングの融合や、ショール―ミーング(店舗で実物を確かめてECサイトで購入する流れのこと)などを取り入れ、消費者がただ商品を購入するだけでなく「楽しいひと時を過ごせる」ように工夫することが大切です。
また、ショッピングモールでの買い物体験にテクノロジーを活用し、AR体験による来店促進やAI接客によるサポートを行うことで、顧客満足度を上げる必要もあります。
2つ目は、サステナブルな取り組みや体験型消費の増加です。環境への配慮は今や企業にとっても必須の課題となっており、SDGs(持続可能な開発目標)への取り組みがショッピングモールに求められています。ショッピングモールでも環境に配慮した商品の販売や環境に優しい取り組みを行い、社会的責任を果たしていることを顧客に伝えなくてはなりません。
さらに、ショッピングモールではただ物を売るのではなく、体験型消費を意識することも不可欠です。
| ※体験型消費:体験や経験に価値を置いて消費する行動 |
イベントや限定販売を行う、買い物自体をワクワクできる工夫を行うなど、ショッピングモールが訪れる価値のある場所であるとアピールできれば、競合との差別化を図れます。
ショッピングセンターの進化には、次の2点が不可欠です。
1つ目は、地域コミュニティのハブとしての役割を果たすこと。地域コミュニティのハブになることで、ショッピングセンターがただ買い物をする場所なだけでなく、地域住民の生活の一部となり、競合との差別化が図れます。
具体的には、ショッピングセンター内にイベントスペースやコミュニティスペースなど、地域に住む方々が交流できる場所を提供しましょう。ショッピングセンターの中には、敷地内に芝生を設けて、訪れる方々の会話が弾むようになったケースもあります。
その他にも、地域におけるイベントや文化活動と連携することで、地域に住む方の関心を集めることもできます。
2つ目は、デジタル化とリアル店舗の融合です。このために、OMO(Online Merges with Offline)戦略が必須といえるでしょう。OMOとは、オンラインとオフラインが融合したことを意味する言葉。OMO戦略を取り入れ、顧客にとって高品質で便利な購入体験を提供することがショッピングセンターの進化には必要です。
| <OMO戦略の例> ・ECサイトで注文したものを実店舗で受け取る店頭受け取り ・自宅配送 ・購買履歴をもとに商品を紹介するデジタルサイネージなど |
便利な体験を提供できるショッピングセンターが、今後は顧客から選ばれる鍵となります。
ショッピング施設の活用法として、さまざまなビジネスを取り入れることも選択肢に入ります。
1つ目は、ポップアップストアや期間限定ショップの展開による集客です。ポップアップストアや期間限定の店舗は話題性が高く、顧客の関心や興味が引きやすいのが特徴。常設店舗ではないためイベント感や希少さがあり、「今行かなくては」という心理を働かせることで、来店者を増やす効果が期待できます。
また、ポップアップストアや期間限定ショップはSNSでの共有やメディアでの取り上げを通じて、情報の拡散による集客効果も狙えるでしょう。
2つ目は、テナントの誘致やイベント開催により、施設価値を向上させることです。期間限定の施策に加えて、常設店の強化や魅力ある施策を進め、「行きたくなるショッピング施設」へと成長させます。
テナントの誘致は、特に集客力の高いキーテナントや、幅広い年齢層を集客できる飲食店を呼び込むことが鍵です。飲食店では、イートイン以外にもテイクアウトができるお店を充実させることで、ついで買いを促す戦略が効果的といえます。
さらに、流行となっている店舗を旬のタイミングで定期的に誘致することで、新しい顧客を常に引き寄せることが可能です。
イベント開催についても、施設内の滞在時間を増やして消費を促進させるだけでなく、新規客の来店を促す効果が期待できます。イベントはSNSやメディアに取り上げられれば、施設自体のプロモーションにも繋がるでしょう。
これからのショッピング施設は単なる買い物の場を超えて、多様なビジネスを取り入れることで顧客の訪れる理由を提供し、施設全体の価値を高めることが求められます。
ショッピングモールやショッピングセンターでイベント開催するならショップカウンターがおすすめです。ショップカウンターでは、東京都を中心に日本全国各地にあるショッピングモールやショッピングセンターのイベント開催場所の検索・予約が可能です。

2024年8月3日

2024年7月16日

2021年1月25日

2017年2月22日

2024年8月10日
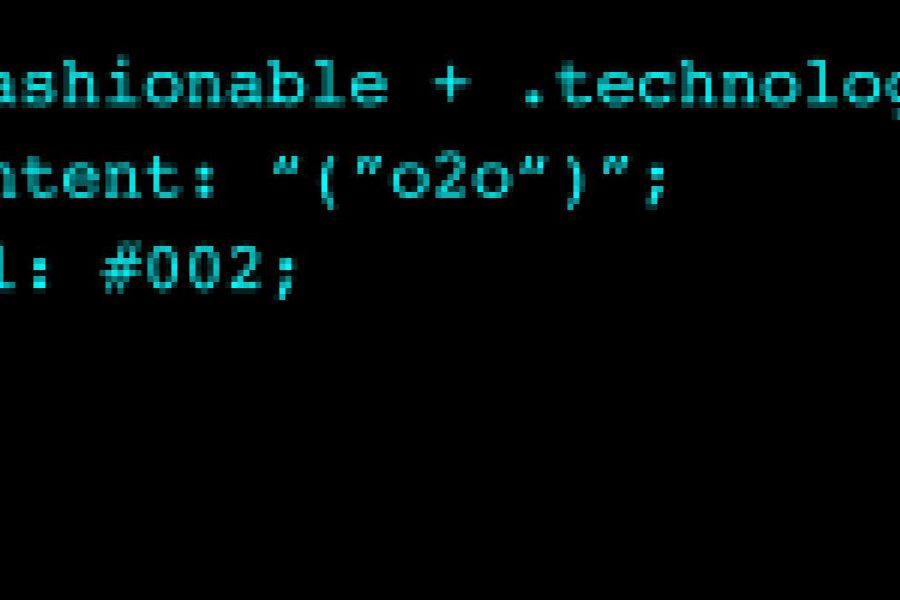
2015年12月28日

2024年11月15日

2017年2月7日
2016年5月12日
2020年2月14日
2024年4月7日
2025年1月27日
2024年6月23日
2024年4月28日
2024年10月13日
2024年9月7日