出店場所を検討する際に必ず行うスペースの下見。 スペースそのものだけではなく、スペース周辺の環境や駅からの道のりなどエリア環境も重要なチェックポイントです。

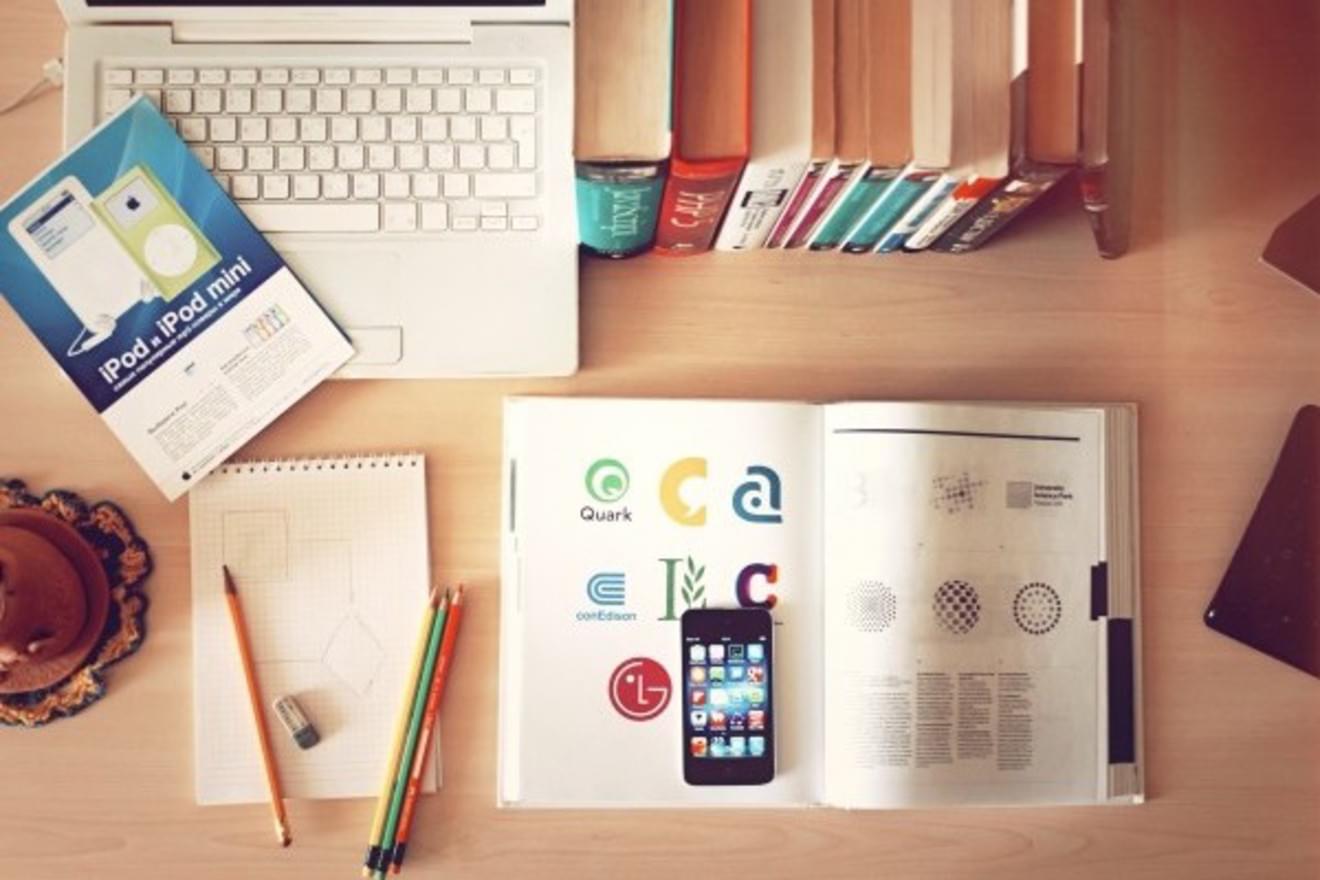
出店場所を検討する際に必ず行うスペースの下見。
スペースそのものだけではなく、スペース周辺の環境や駅からの道のりなどエリア環境も重要なチェックポイントです。
今回はその中でも売り上げを大きく左右する競合店調査のポイントをお届けします。
目次
まず、出店を検討する際になぜ競合店の調査が必要なのでしょうか?
その理由のひとつは、競合店があることで出店のイメージがしやすいということです。
「競合店舗が多い=ライバルが多いから出店を諦める」ではなく、競合店舗が集まっていることで特定の目的をもったお客様が集まるエリアであるともいえます。
例えば表参道にはアパレル系のショップが多かったり、神保町の古書店街や秋葉原の電気街などがその典型です。
すでに既存のショップで成功しているところを観察することで、そのエリアに足を運ぶ層が好む雰囲気や店づくりを学ぶことができます。
出店前の下見の際にはスペースの内見だけではなく、いくつか気になるショップをピックアップして調査するようにしましょう。
その際はアパレル、雑貨、食品といった業種別の競合だけではなく、年齢層や嗜好ターゲットが近いショップを観察しておくとより効果が高いでしょう。
競合店調査でまず注目すべきはそのショップの客層。
年齢はもちろん、それとなくファッションや持ち物を観察してライフスタイルを想像しましょう。
ショップの紙袋を手にしている場合は特に要チェックです。
またできるだけピークタイム(週末の午後など)に訪れるようにし、混み具合をチェックします。
競合店舗のピークタイムの状況を知ることで、おおまかな来店客数を予測することができます。
もちろん立地や知名度によっても客数は大きく異なるため、少なくとも3、4店舗は見比べてみて自分がショップをオープンした場合の来店客数を予測しましょう。
※ “TG(交通発生源)”についてはこちら
駅や商業施設といったTGから競合店舗への動線を観察することで、その店舗の立地の良し悪しを考察することができます。
自分が出店する予定のスペースが競合店舗と比べてTGに近く人通りが多いようであれば、ターゲットとなるお客様を呼び込める確率が高くなります。
逆に競合店舗の方が明らかに立地が良い場合は見せ方や事前の宣伝に工夫をするようにしましょう。
競合店舗の中に入って観察する場合には、広さに対する商品点数もチェックしておきましょう。
たくさんの商品の中から欲しいものを見つける宝探しのような雰囲気が好まれるのか、限られた商品点数ですっきりと落ち着いた空間が好まれるのかはそのエリアや立地によっても異なるため、競合店舗の展開の仕方は非常に参考になります。
基本的には商品の単価が高くなるほど商品点数を絞ってすっきりと見せる傾向がありますが、どのくらいの価格帯から「高い」と感じるのかを知るという意味でも競合店舗の商品展開はチェックしておくことをおすすめします。
「SHOPCOUNTER」は、ポップアップストア・催事・展示会などの出店/出展場所の予約がオンライン上でできるプラットフォームです。ショッピングモール、スーパーマーケット、百貨店、商店街、駅ナカ、オフィスビル、撮影スタジオ、展示会場など様々な商業スペースの検索・予約が可能です。
今すぐお探しでない方もアカウント作成 することで、新着やおすすめスペース等のお役立ち情報を受け取ることができますので、ぜひご登録ください。

ポップアップストア・催事イベントにおすすめなスペースや、ノウハウ・事例を紹介いたします。

2015年9月19日

2015年9月19日

2015年12月3日

2016年4月6日

2015年9月19日

2015年11月23日

2015年10月2日

2016年8月10日
2016年5月12日
2025年5月30日
2020年2月14日
2025年6月2日
2025年1月27日
2025年10月20日
2024年4月28日
2016年1月15日

2025年12月8日

2025年12月4日

2025年11月4日

2025年10月20日

2025年10月20日

2025年10月7日

2025年9月26日

2025年8月27日