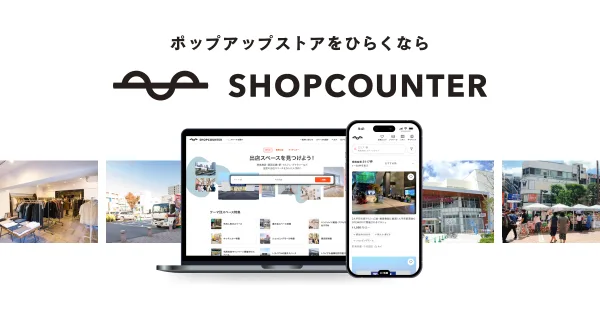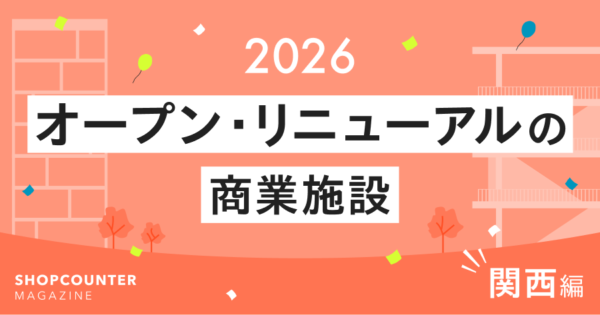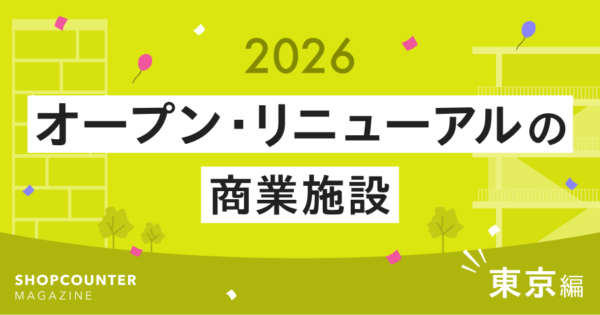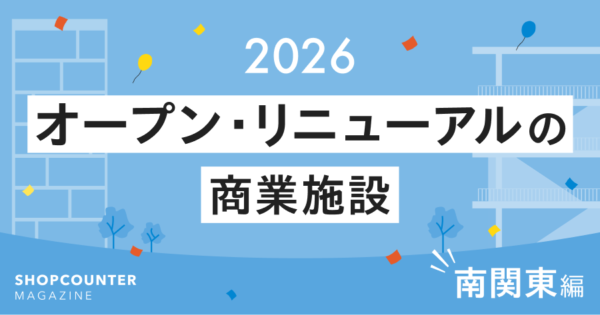プロダクト・プレイスメントとは?効果とメリットを解説
映画やテレビドラマなどにも使われているプロダクト・プレイスメントという手法は、自然に受け入れられ、認知度アップを期待できます。本記事ではポップアップストアにも取り入れられるプロダクト・プレイスメントについて、定義と概要、種類と手法、効果とメリット、成功事例について解説します。

記事のポイント
1.Z世代向けにはテレビCM以外で接点を創出できるプロダクト・プレイスメントに注目が集まっている
2.プロダクト・プレイスメントはコンテンツのストーリーに沿った露出で効果を発揮
3.映画やドラマ期間に合わせたポップアップストア出店には装飾の自由度が高い路面店がおすすめ
目次
1. プロダクト・プレイスメントの定義と概要
プロダクト・プレイスメントとは何か
プロダクト・プレイスメントとは、映画やドラマなどのコンテンツ内に広告したい商品を組み込み、自然な形で訴求するやり方です。
プロダクト・プレイスメントはコンテンツ内で溶けこむように商品やロゴなどを露出させることで、CMなどとは違い、見せられている感じや嫌悪感なく、印象付けることが可能です。
プロダクト・プレイスメントの歴史
アメリカでは1955年に公開された映画『理由なき反抗』が始まりといわれています。(諸説あり)
主演のジェームズ・ディーンが劇中で櫛を取り出し、髪を整えるシーンが幾度となく登場。公開後に、ジェームズ・ディーンが使っていた櫛はどの店で買えるのかという問い合わせが殺到したそうです。この話からヒントを得た映画関係者が、新しいビジネスモデルとしてタイアップを開始しました。
プロダクト・プレイスメントの手法が注目を浴びる様になったのは、1982年公開の映画『E.T.』からです。さまざまな商品が映画に登場しましたが、特にハーシー社が手掛けるチョコレートが映画の大ヒットと相まって、世界中で大人気となりました。
プロダクト・プレイスメントは昨今では、コマーシャルが基本的には流れない韓国ドラマで多く見られています。
2. プロダクト・プレイスメントの種類と方法
映画・テレビ番組での活用
映画では商品が映っているだけでなく、007シリーズのように主人公が身に付けることで宣伝効果を発揮するパターンもあります。一つの作品で、複数の企業の商品やサービスが登場する場合もあります。
テレビでは、ドラマなどでデジタル技術を活用し、本来なかった場所にスポンサーのポスターなどを後付けで配置。自然な流れで商品やサービスの情報を表示させています。
ソーシャルメディアとインフルエンサーの役割
プロダクトプレイスメントは、ソーシャルメディアと併用することも効果的です。ソーシャルメディアを活用したプロダクト・プレイスメントは、ソーシャルメディアの投稿の中に小物として自社製品を置くことで、注目を集めます。
ソーシャルメディアにおいてプロダクトプレイスメントを活用する際は、インフルエンサーは切っても切り離せない存在といえるでしょう。各分野において大勢から支持を集めるインフルエンサーの投稿にさりげなく商品やサービスが映るようにすることで、認知度アップを図れます。
デジタルメディアとゲーム内広告
デジタルメディア
デジタルメディアの利用としては、映像作品とあわせて活用する技術開発が進んでいます。例えば機械学習やレンダリング技術を用いて、映像作品内にバーチャルの広告を挿入することで、視聴者の邪魔にならないように商品やサービスを表示させることが可能です。
その他にも、デジタルメディアの視聴者の属性に合わせて商材を出し分けるといった配信を行う技術もあります。
ゲーム
プロダクト・プレイスメントは、ゲームでも可能です。ゲーム内で使用するアイテムを、実在するブランドのアイテムにすることで自然な形で登場させることで、認知度アップを図れます。
2015年に発売された「ファイナルファンタジーXV」では、ゲーム内のキャラクターがキャンプをするシーンがあり、その際に使われていたのが実在するColeman(コールマン)でした。ゲーム内に自然に登場させることで、若い世代への訴求も行えます。
3. プロダクト・プレイスメントの効果とメリット
ブランド認知度の向上
プロダクト・プレイスメントは、コンテンツに登場する俳優やキャラクターが使用することで、ブランド認知度の向上が期待できます。なぜなら、展開されるストーリーや登場人物の言動に登場する商品は、物語を見ている視聴者の意識にスッと自然に入り込んでいくからです。
ドラマや映画などにさりげなく登場する商品は、CMなどと違い視聴者が見たいコンテンツに割り込むことがないため、ストレスを与えず、ネガティブなイメージを抱かれにくいのもメリットといえます。
また、プロダクト・プレイスメントは特定の俳優やタレント、作品などのファンだけでなく、それ以外の層にもアプローチが可能な点もメリット。ブランド認知度の向上を、幅広く図れる手法です。
消費者行動への影響
プロダクト・プレイスメントは、消費者の行動にも影響を与えます。消費者がコンテンツを見ることで、気になった商品を実際にwebで検索したり、友人や家族と話題にしたり、商品のホームページを実際に見に行ったりという行動を促すことが可能です。
他のマーケティング手法との比較
プロダクト・プレイスメントは他のマーケティング手法と異なり、スキップされません。数々の情報を見ることになるデジタル広告の世界では、ユーザーにとって強制的に見せられるコンテンツは、視聴時にストレスを感じるもの。他のマーケティング手法ではスキップされて視聴者に届かない可能性がありますが、プロダクト・プレイスメントならストーリーに溶けこんでおり、スキップされず視聴者の記憶に残ります。
また、プロダクト・プレイスメントは自然な形で商品などが登場するため、無理矢理広告を見せつけられている印象がありません。消費者にとってはコンテンツを中断されることなく楽しめ、かつマイナスイメージを抱かれにくい点が、他の手法との違いです。
4. プロダクト・プレイスメントの成功事例
映画・テレビでの成功事例
映画の成功事例:『天気の子』
プロダクト・プレイスメントにおいて例としてよく挙げられるのが、大ヒットした映画の『天気の子』です。新海誠監督によって作られた2019年7月公開の映画では、サントリーや日清食品など実在するメーカーの飲食物や、バイトルなどのサービスが劇中に登場しています。
ドラマの成功事例:『逃げるは恥だが役に立つ』
TBSのドラマである『逃げるは恥だが役に立つ』では、さまざまなメーカーの商品やサービスが登場。(株式会社Mizkanの白だしやアート引越センターなど)
作品中でも特に目立ったのは、メインキャラクターの一人が運転する黄色い車の日産のジュークです。ドラマの日常生活シーンにおいて企業ブランドが登場しても、ネガティブな印象を抱かれることがありませんでした。
ドラマの成功事例:『愛の不時着』
韓国ドラマである愛の不時着も、数々のプロダクト・プレイスメントが登場しています。韓国国内の大手フライドチキンのチェーン店や、装飾品のメーカーであるスワロフスキー、その他にも自動車が登場しました。
高視聴率が望めるドラマにサラッと登場させることで、視聴者に商品の存在感を認識させたケースといえるでしょう。
ソーシャルメディアでの成功事例
人気コンテンツのちいかわは、Xにマンガが掲載されているだけでなくフジテレビ系列のめざましテレビや、YouTube、有料動画配信サイトでアニメも放映されています。
マンガやアニメにて印象的なのが、登場人物の一人であるハチワレが実在する食品のチャルメラを「チャリメラ」と言い間違えるシーン。公開された動画にたくさんのコメントが集まっているだけでなく、実際に商品としてチャリメラが販売されました。
Xでは、アニメの公開や商品のチャリメラが発売されて以来、たびたび #ちいかわ や #チャリメラ などのハッシュタグが付けられてポストが投稿され、ちいかわやチャルメラが話題になっています。
5. プロダクト・プレイスメント導入時の注意点
法的および倫理的考慮事項
現在、日本国内ではプロダクト・プレイスメントにおいて、創作物の中に実在する商品やブランドを登場させることに関する広告規制は行われておりません。
しかし、EUにおいては現在、プロダクト・プレイスメントを行う際はその旨を明示しなくてはなりません。今後時代が変化することで、EUのような規制がされる可能性は十分にあります。
プロダクト・プレイスメントは視聴者側からステルスマーケティングと認識されるリスクが避けられません。ステルスマーケティングと判断され評判を落とさないためにも、映像作品の場合はエンドロールに事業者名を入れる、YouTubeなら動画や説明文にブランド名や企業名を明示するといった配慮を行い、リスクを未然に防ぐことが求められます。
消費者の受け取り方と反応
プロダクト・プレイスメントは、消費者の受け取り方や反応次第で好印象から悪印象まで変わるもの。使われ方が不自然であれば、視聴者は不快なイメージを抱きます。その他にも、使われ方が良くないと、大金をかけても視聴者の記憶にほとんど残らない場合もあります。
プロダクト・プレイスメントはコンテンツ内の使われ方次第で、商品やブランドに対する受け取り方や反応が変わるため、慎重に活用するのが良いです。
過剰なプレイスメントのリスク
プロダクト・プレイスメントとは、映画やテレビなどにあくまで自然な形で登場させることで、訴求効果が高められる方法。過剰に登場させることでステルスマーケティングと疑われる・アピールが過ぎると捉えられると、商品やブランド、企業自体のイメージダウンに繋がります。
過剰なプレイスメントによるリスクを避けるためにも、あくまでも映画やテレビなどのコンテンツにおける世界観を大事にして、多過ぎず自然な形で入れることが大事です。
まとめ
マーケティングの手法の一つであるプロダクト・プレイスメントは、より自然な形で自社の商品やサービスを、コンテンツに触れる方にアピールする手法です。
コンテンツに自然な形で盛り込み、適切に利用して認知度アップに役立てましょう。
関連記事
出店場所をお探しの方へ
「SHOPCOUNTER」は、ポップアップストア・催事・展示会などの出店/出展場所の予約がオンライン上でできるプラットフォームです。ショッピングモール、スーパーマーケット、百貨店、商店街、駅ナカ、路面店、撮影スタジオ、展示会場など様々な商業スペースの検索・予約が可能です。
今すぐ出店スペースをお探しでない方もアカウント作成 することで、新着やおすすめスペース等のお役立ち情報を受け取ることができますので、ぜひご登録ください。
参考
株式会社インテージ『プロダクトプレースメントとは』
INFO CUBIC『プロダクト・プレイスメントとは?~世界観を壊さない優れた広告フォーマット、海外事例など~』
AKATSUKI『プロダクトプレイスメントの歴史』『プロダクトプレイスメントの強み』『プロダクトプレイスメントはステルスマーケティングではないのか?』
APiE『プロダクトプレイスメントとは』
PR TIMES『「山之内すずのイキなSDGs旅」番組にて、AI技術を用いたデジタル・プレイスメント広告(Virtual In-Content ads)を実施』
ZEALL『さりげなくアピールできる!プロダクトプレイスメント』
AdSELL『【インフルエンサーマーケティング】失敗しないインフルエンサーの選定と広告効果測定を簡単にわかりやすく解説!』
Truestar Consulting Group『PPL(プロダクトプレイスメント)は映画やドラマだけじゃない?』
MarkeZine『プロダクトプレイスメント広告、視聴者の5割は「不快に感じない」と回答/ガイエ調査』Media Innovation『嫌われない広告の形とは…?プロダクトプレイスメントに関する調査結果』
デジマクラス『プロダクトプレイスメントの事例を解説!注目の理由は?プロダクトプレイスメントのメリットや今後の動向についてもご紹介!』
ジェイアール東日本企画キクコト『【映画タイアップ成功事例】CMのためにオリジナルシーンを描き起こし!
HINAGIKU『Digital Placement』
PageZ『古くて新しい広告手法!プロダクトプレイスメントとは?』
SUNGROVE『プロダクトプレイスメントとは?日本の事例と効果・メリット』
YouTube総研『パートナーが投稿者に依頼して動画を紹介してもらうプロダクトプレースメントとは?』

ポップアップストア・催事イベントにおすすめなスペースや、ノウハウ・事例を紹介いたします。